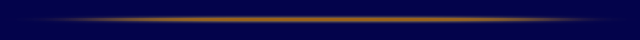
胡蝶の夢~私の最愛~⑪【夢路・ゆめじ】
第32章 変化(へんげ)
が、これ以上、脇坂の話を平静に聞いてはいられなかったのもまた事実だ。自分が黎次郎と引き離されている間、泰雅が黎次郎を可愛がり慈しんでいた。それは何も悪しきことではなく、むしろ歓ぶべきことであった。
なのに、素直には歓べない。黎次郎は今、自分を見たとしても、泉水が母親だとは認識できないだろう。それは当然のことだ。物心つく前に、泉水の手から離れ、遠い江戸へと赴いたのだ。だが、黎次郎と離れた淋しさに自分が耐えている間、泰雅だけは黎次郎と親子らしい刻を過ごしていたのだと思うと―、妬ましさと怒りを感じずにはいられない。
「済まぬ。その話はもう良い。黎次郎の様子はよう判った。これよりも、あの子のことをくれぐれも頼みます」
「もとより、この脇坂倉之助、身命に賭しても、若君さまの御事、必ずやお守り致します」
脇坂の言葉は、どこまでも頼もしかった。
泉水は、ぼんやりと庭を見つめた。
白い紫陽花が初夏の陽光を浴びている。
その穢れなき色が、泉水の眼を眩しく射た。
「それよりも、脇坂どの。私はつくづく浅ましき我が身が厭わしい」
「―」
脇坂は、それに対しては無言であった。
短い静寂が流れた。
泉水は庭から脇坂に視線を戻す。
「一度は御仏にお仕えする身となりながら、こうして俗世に立ち返り、なすこともなく、無為な日々を過ごしておるばかりじゃ」
「奥方さま、奥方さまは先刻、仰せになられましたな。五年前、それがしが黎次郎君を連れ去ったことは致し方のなかったことだと」
脇坂が静かな声音で言った。
泉水が脇坂の顔を見る。
五年の間に白髪がやや目立つようになった脇坂は、以前より表情や雰囲気が随分とやわらぎ、穏やかになったようだ。
「それならば、奥方さまが還俗なされたこともまた、致し方になきことにござりましょう。奥方さまが月照庵をお守りになるために、やむなく俗世に戻られたこと、この脇坂はよう存じております」
脇坂のこの言葉は、今の泉水の心に滲みた。
「のう、脇坂どの。殿は何ゆえ、私をお苦しめになられるのであろう」
泉水がどこまで逃げても、泰雅は執拗に追いかけてきて、捉えられてしまう。不覚にも涙が滲み、泉水は慌てて眼をしばたたいた。
なのに、素直には歓べない。黎次郎は今、自分を見たとしても、泉水が母親だとは認識できないだろう。それは当然のことだ。物心つく前に、泉水の手から離れ、遠い江戸へと赴いたのだ。だが、黎次郎と離れた淋しさに自分が耐えている間、泰雅だけは黎次郎と親子らしい刻を過ごしていたのだと思うと―、妬ましさと怒りを感じずにはいられない。
「済まぬ。その話はもう良い。黎次郎の様子はよう判った。これよりも、あの子のことをくれぐれも頼みます」
「もとより、この脇坂倉之助、身命に賭しても、若君さまの御事、必ずやお守り致します」
脇坂の言葉は、どこまでも頼もしかった。
泉水は、ぼんやりと庭を見つめた。
白い紫陽花が初夏の陽光を浴びている。
その穢れなき色が、泉水の眼を眩しく射た。
「それよりも、脇坂どの。私はつくづく浅ましき我が身が厭わしい」
「―」
脇坂は、それに対しては無言であった。
短い静寂が流れた。
泉水は庭から脇坂に視線を戻す。
「一度は御仏にお仕えする身となりながら、こうして俗世に立ち返り、なすこともなく、無為な日々を過ごしておるばかりじゃ」
「奥方さま、奥方さまは先刻、仰せになられましたな。五年前、それがしが黎次郎君を連れ去ったことは致し方のなかったことだと」
脇坂が静かな声音で言った。
泉水が脇坂の顔を見る。
五年の間に白髪がやや目立つようになった脇坂は、以前より表情や雰囲気が随分とやわらぎ、穏やかになったようだ。
「それならば、奥方さまが還俗なされたこともまた、致し方になきことにござりましょう。奥方さまが月照庵をお守りになるために、やむなく俗世に戻られたこと、この脇坂はよう存じております」
脇坂のこの言葉は、今の泉水の心に滲みた。
「のう、脇坂どの。殿は何ゆえ、私をお苦しめになられるのであろう」
泉水がどこまで逃げても、泰雅は執拗に追いかけてきて、捉えられてしまう。不覚にも涙が滲み、泉水は慌てて眼をしばたたいた。
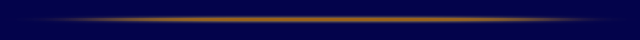
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える