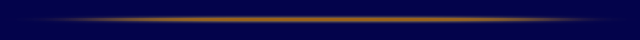
胡蝶の夢~私の最愛~⑪【夢路・ゆめじ】
第30章 花惑い
男の眼を愉しませるために、きらびやかな打掛を身に纏う―、なぞと想像しただけでも身の毛がよだつようだ。元々、美しい打掛や小袖、女らしい恰好は性に合わず、男装してはお忍びで江戸の町に出かけていた泉水である。出家して俗世と縁を絶って以後は尚更、そのような華美な衣装への執着はなくなった。むしろ、美しく女らしく装うことが泰雅を歓ばせるため、満足させるためだと思えば、虫酸が走る。
「奥方さま」
泉水の前に、そっと草履が揃えて差し出される。その草履は泉水が月照庵から履いてきた白い鼻緒の草履であった。泉水は礼を小さな声で述べ、草履を履く。
「奥方さま、そのように意地をお張りになられますな」
泉水は首を振った。
「私は意地など張ってはおらぬ。河嶋、心ききたるそなたにだとて、この私の胸の内は判らぬか。私は一度、俗世を捨てた身、いわば世捨て人じゃ。尼がそのようなきらびやかな打掛を身に纏うなぞ笑止」
「そのことならば、ご心配には及びませぬ。奥方さまには早々に還俗して頂きます」
「え―」
刹那、泉水の大きな眼が河嶋を射るように見開かれた。
一瞬の静寂の後、泉水が唇を震わせた。
「今、今、何と申した?」
河嶋がいかにも気の毒げな表情で見つめていた。
「これは、殿の御意にございます」
そうとでも言えば、言い訳の代わりにでもなると言いたげな口ぶりであった。河嶋にしてみれば、このような残酷極まりなき宣告を突きつける役目は果たしたくはなかったろう。
「還俗―、この身に再び俗世に還れと?」
それは、ある意味で、榊原の屋敷に戻れと言われたとき以上に、泉水に衝撃を与えたかもしれない科白であった。
「いやじゃ、それだけは絶対にいやじゃ。私を愚弄するにも程があるというもの。そのような辱めを受けるならば、私は、私は」
泉水は泣きながら首を烈しく振り続けた。
「では、ご自害なされませ」
河嶋が懐から何やら差し出す。つと眼前に差し出されたのは、ひとふりの懐剣。
小さな短刀をスと眼の前にかざし、河嶋は微笑んだ。
「奥方さま」
泉水の前に、そっと草履が揃えて差し出される。その草履は泉水が月照庵から履いてきた白い鼻緒の草履であった。泉水は礼を小さな声で述べ、草履を履く。
「奥方さま、そのように意地をお張りになられますな」
泉水は首を振った。
「私は意地など張ってはおらぬ。河嶋、心ききたるそなたにだとて、この私の胸の内は判らぬか。私は一度、俗世を捨てた身、いわば世捨て人じゃ。尼がそのようなきらびやかな打掛を身に纏うなぞ笑止」
「そのことならば、ご心配には及びませぬ。奥方さまには早々に還俗して頂きます」
「え―」
刹那、泉水の大きな眼が河嶋を射るように見開かれた。
一瞬の静寂の後、泉水が唇を震わせた。
「今、今、何と申した?」
河嶋がいかにも気の毒げな表情で見つめていた。
「これは、殿の御意にございます」
そうとでも言えば、言い訳の代わりにでもなると言いたげな口ぶりであった。河嶋にしてみれば、このような残酷極まりなき宣告を突きつける役目は果たしたくはなかったろう。
「還俗―、この身に再び俗世に還れと?」
それは、ある意味で、榊原の屋敷に戻れと言われたとき以上に、泉水に衝撃を与えたかもしれない科白であった。
「いやじゃ、それだけは絶対にいやじゃ。私を愚弄するにも程があるというもの。そのような辱めを受けるならば、私は、私は」
泉水は泣きながら首を烈しく振り続けた。
「では、ご自害なされませ」
河嶋が懐から何やら差し出す。つと眼前に差し出されたのは、ひとふりの懐剣。
小さな短刀をスと眼の前にかざし、河嶋は微笑んだ。
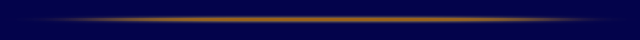
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える