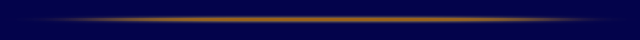
胡蝶の夢~私の最愛~⑪【夢路・ゆめじ】
第30章 花惑い
脇坂の眼には憐憫とも同情ともつかぬ色がありありと浮かんでいた。泉水は知らぬことではあったが、泰雅が泉水を連れ戻すに至って、脇坂は猛反対したのだ。
―既に仏門に入られ、尼君となられたお方をむざと憂き世に引き戻すは、人の情にもまた、この世の理(ことわり)にも外れる仕儀にござります。奥方さまの御事はお諦めになられ、そっとしておいて差し上げるのが人の道に叶うことにはございますまいか。
脇坂は守役として、泰雅を幼い頃から見守ってきた。泰雅も幼時からこの老練な家老には一目置いていた。泰雅が父泰久を失って家督を継いだのは十二歳のときであった。まだ前髪立ちの童姿であったのを、家督を継いだからと急遽元服をしたほどである。その頃から、泰雅にとって脇坂の存在は更に重要性を増し、脇坂の言ならば、たとえ臣下であろうと真剣に耳を傾けていたのだ。
が、事ここに至り、泰雅はその脇坂の言葉すら一向に聞こうとはしなかった。以前から、そうであった。泉水に対して、度の越えた執心を見せ、こだわっていた。
かつて〝女狂い〟と囁かれていた遊興癖も一切なくなり、領地の政治にも積極的に取り組もうとしていたし、わずかな間であっても彼本来の英明さを発揮していたのだ。
それが、泉水のこととなると、まるで人が変わったかのように異常なまでの執着を見せる。奥向きにある泉水の寝所からは夜毎、すすり泣きや悲鳴が聞こえている―と、奥女中たちの間ではひそやかな噂が流れていた。夫婦の閨でどのような光景が繰り広げられているのか、脇坂は知らないし、また知りたくもなかった。ただ、泰雅が泉水をどのように扱っていたのかは大方の想像はつくというものだ。
誰が見ても、泉水に対する泰雅の寵愛は尋常ではなかった。いつだったか、家臣の誰かが冗談でふと洩らしたことがある。
―真を申せば、殿はお方さまを他の誰の眼にも触れさせず、ご寝所に閉じ込めてでもおかれたいのではないか。
―そのようなこと、万が一、殿のお耳に入れば、大変なお怒りをかうであろう。滅多なことを口にせぬものぞ。
脇坂がたしなめると、まだ若い家臣は青褪めたものだった。冗談でも話題が泉水のことであるだけに、泰雅がどのような反応を示すかは判らなかった。それほど泉水に関することとなれば、泰雅は過剰な反応を見せていた。
―既に仏門に入られ、尼君となられたお方をむざと憂き世に引き戻すは、人の情にもまた、この世の理(ことわり)にも外れる仕儀にござります。奥方さまの御事はお諦めになられ、そっとしておいて差し上げるのが人の道に叶うことにはございますまいか。
脇坂は守役として、泰雅を幼い頃から見守ってきた。泰雅も幼時からこの老練な家老には一目置いていた。泰雅が父泰久を失って家督を継いだのは十二歳のときであった。まだ前髪立ちの童姿であったのを、家督を継いだからと急遽元服をしたほどである。その頃から、泰雅にとって脇坂の存在は更に重要性を増し、脇坂の言ならば、たとえ臣下であろうと真剣に耳を傾けていたのだ。
が、事ここに至り、泰雅はその脇坂の言葉すら一向に聞こうとはしなかった。以前から、そうであった。泉水に対して、度の越えた執心を見せ、こだわっていた。
かつて〝女狂い〟と囁かれていた遊興癖も一切なくなり、領地の政治にも積極的に取り組もうとしていたし、わずかな間であっても彼本来の英明さを発揮していたのだ。
それが、泉水のこととなると、まるで人が変わったかのように異常なまでの執着を見せる。奥向きにある泉水の寝所からは夜毎、すすり泣きや悲鳴が聞こえている―と、奥女中たちの間ではひそやかな噂が流れていた。夫婦の閨でどのような光景が繰り広げられているのか、脇坂は知らないし、また知りたくもなかった。ただ、泰雅が泉水をどのように扱っていたのかは大方の想像はつくというものだ。
誰が見ても、泉水に対する泰雅の寵愛は尋常ではなかった。いつだったか、家臣の誰かが冗談でふと洩らしたことがある。
―真を申せば、殿はお方さまを他の誰の眼にも触れさせず、ご寝所に閉じ込めてでもおかれたいのではないか。
―そのようなこと、万が一、殿のお耳に入れば、大変なお怒りをかうであろう。滅多なことを口にせぬものぞ。
脇坂がたしなめると、まだ若い家臣は青褪めたものだった。冗談でも話題が泉水のことであるだけに、泰雅がどのような反応を示すかは判らなかった。それほど泉水に関することとなれば、泰雅は過剰な反応を見せていた。
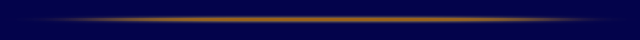
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える