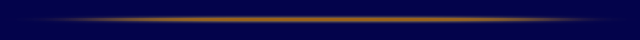
胡蝶の夢~私の最愛~⑪【夢路・ゆめじ】
第26章 別離
その後、泉水には逢うこともなく時は過ぎ、所詮はゆきずりの儚い恋だったのだと諦めていたのだけれど、思いもかけず、実の母が結んだ庵で泉水と再会することになる。九ヶ月ぶりに逢った泉水は良人から逃れ、この寺に身を寄せていた。やがて懐妊していることを知った泉水は絶望のあまり、自ら川に入り生命を絶とうとさえしたのだ。それを止めたのが夢五郎であった。
叶うならば、泉水の傍にいて、ずっと見守っていたい。泉水は男を受け容れることができない。それは何も泉水が悪いわけではなく、生まれ持った哀しい性(さが)であった。榊原泰雅は、泉水をあまりにも烈しく愛するがあまり、泉水のすべてを我が物としようとし、泉水を心身共に傷つけた。夢五郎は間違っても、泰雅の二の舞は踏みたくない。たとえ泉水に惚れてはいても、女を哀しませてまで想いを遂げようとは思わない。
惚れた女と添えぬ運命(さだめ)であれば、せめてその傍にいて、女と子どもを守ってやりたい。そう願ってきた。だが、運命はそう容易く思いどおりにはゆかないものらしい。泉水と自分を引き合わせた気紛れな運命は、またしても自分たちを引き離そうとしている。
夢五郎は愛しい女の面影を瞼に強く刻みつけておこうと、食い入るようにその横顔を見つめた。
背後にふと人の気配がしたような気がして、泉水は振り向いた。
「夢五郎さん」
相変わらず〝夢五郎〟と呼ぶのは、夢五郎自身が泉水の前では〝藤原頼房〟ではなく、〝夢売りの夢五郎〟でいたいのだと言ったからだ。立ち上がろうとした泉水に、夢五郎は眼顔で首を振った。
「そのままで良い」
膝の上の黎次郎はいつしか眠っていた。
黎次郎を起こさぬようにと気遣ってくれたのだ。いつもながら、夢五郎らしい心遣いであった。
「まあ、この子ったら。つい先刻まで起きて、はしゃいでいたのに」
泉水が笑うと、夢五郎が傍に来て座った。
「しばらく見ぬ間にまた大きくなったな」
まるで、しばらくぶりに我が子を見る父親のような表情で黎次郎の寝顔を覗き込む。
「二ヶ月ぶりですもの、子どもは大きくなります」
そう言ってから、自分の口調が甘えるような、少し拗ねたような響きがあることに愕然とする。
叶うならば、泉水の傍にいて、ずっと見守っていたい。泉水は男を受け容れることができない。それは何も泉水が悪いわけではなく、生まれ持った哀しい性(さが)であった。榊原泰雅は、泉水をあまりにも烈しく愛するがあまり、泉水のすべてを我が物としようとし、泉水を心身共に傷つけた。夢五郎は間違っても、泰雅の二の舞は踏みたくない。たとえ泉水に惚れてはいても、女を哀しませてまで想いを遂げようとは思わない。
惚れた女と添えぬ運命(さだめ)であれば、せめてその傍にいて、女と子どもを守ってやりたい。そう願ってきた。だが、運命はそう容易く思いどおりにはゆかないものらしい。泉水と自分を引き合わせた気紛れな運命は、またしても自分たちを引き離そうとしている。
夢五郎は愛しい女の面影を瞼に強く刻みつけておこうと、食い入るようにその横顔を見つめた。
背後にふと人の気配がしたような気がして、泉水は振り向いた。
「夢五郎さん」
相変わらず〝夢五郎〟と呼ぶのは、夢五郎自身が泉水の前では〝藤原頼房〟ではなく、〝夢売りの夢五郎〟でいたいのだと言ったからだ。立ち上がろうとした泉水に、夢五郎は眼顔で首を振った。
「そのままで良い」
膝の上の黎次郎はいつしか眠っていた。
黎次郎を起こさぬようにと気遣ってくれたのだ。いつもながら、夢五郎らしい心遣いであった。
「まあ、この子ったら。つい先刻まで起きて、はしゃいでいたのに」
泉水が笑うと、夢五郎が傍に来て座った。
「しばらく見ぬ間にまた大きくなったな」
まるで、しばらくぶりに我が子を見る父親のような表情で黎次郎の寝顔を覗き込む。
「二ヶ月ぶりですもの、子どもは大きくなります」
そう言ってから、自分の口調が甘えるような、少し拗ねたような響きがあることに愕然とする。
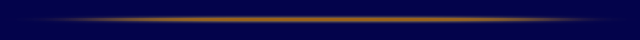
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える