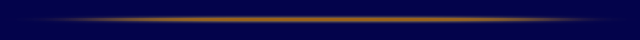
胡蝶の夢~私の最愛~⑪【夢路・ゆめじ】
第26章 別離
「相変わらず、大仰な物言いよのう。たかたがくしゃみ一つくらいで、風邪を引いたやもしれぬと大騒ぎして」
昔から心配性の乳母であったが、こと黎次郎に関することとなると、最早大仰というよりは、見ていられないといった感がある。顔が赤ければ〝お熱があるのでしょうか〟、くしゃみをすれば〝お風邪を召されたのでしょうか〟、まさに孫に盲目になっている祖母そのものいった狼狽えぶりだ。
泉水がそれにろくに取り合おうとしなので、時橋は光照や伊左久に訴える。すると、普段は聡明な尼君や冷静な伊左久までもが大変だと、あたかも天下の一大事が起きたかのように大騒ぎする。
泉水は、そのことにいかほどありがたいと思っているか知れない。時橋はともかく、光照や伊左久は黎次郎とは何の関わりなき人たちだ。なのに、黎次郎を実の孫のように可愛がり、眼に入れても痛くないほどに大切にする。この小さな尼寺で黎次郎は母親からの愛情だけでなく、他の多くの人々の愛情や手に守られ、すくすくと育っているのだ。
「とにかく、大事を取るに越したことはございませぬ。火をもう少し強くしましょう」
時橋は大慌てで火鉢の火をかき起こしたりしている。泉水は温かな気持ちで時橋の背を見つめた。ここ一年で少し髪に白いものが増えた乳母にそっと声をかける。
「ありがとう、時橋」
だが、夢中になって火箸で炭をつついている時橋には聞こえないようだ。
「え、何か仰せになられましたか」
背後を振り返るのに、泉水は微笑んで首を振った。
「いや、何でもない」
「おかしな姫さまでいらっしゃいますこと」
時橋は小首を傾げている。再び背を向けた時橋に、心の中でそっと呼びかけた。
―時橋、いつまでも苦労をかけて済まぬ。
一昨年の秋に榊原邸を突如として出奔して以来、時橋には言うに言えない苦労をかけた。本来なら、泉水が榊原の屋敷を出た今、時橋はここまで付いてくる必要はないのだ。三人の娘たちのいずれかの嫁ぎ先に身を落ち着け、孫の守りをしながら安気に余生を過ごすことができるはずだ。それなのに、こうして泉水の傍につきっきりでいるばかりに、江戸から離れた山の尼寺に暮らし、下女紛いの仕事をして苦労をさせている。
昔から心配性の乳母であったが、こと黎次郎に関することとなると、最早大仰というよりは、見ていられないといった感がある。顔が赤ければ〝お熱があるのでしょうか〟、くしゃみをすれば〝お風邪を召されたのでしょうか〟、まさに孫に盲目になっている祖母そのものいった狼狽えぶりだ。
泉水がそれにろくに取り合おうとしなので、時橋は光照や伊左久に訴える。すると、普段は聡明な尼君や冷静な伊左久までもが大変だと、あたかも天下の一大事が起きたかのように大騒ぎする。
泉水は、そのことにいかほどありがたいと思っているか知れない。時橋はともかく、光照や伊左久は黎次郎とは何の関わりなき人たちだ。なのに、黎次郎を実の孫のように可愛がり、眼に入れても痛くないほどに大切にする。この小さな尼寺で黎次郎は母親からの愛情だけでなく、他の多くの人々の愛情や手に守られ、すくすくと育っているのだ。
「とにかく、大事を取るに越したことはございませぬ。火をもう少し強くしましょう」
時橋は大慌てで火鉢の火をかき起こしたりしている。泉水は温かな気持ちで時橋の背を見つめた。ここ一年で少し髪に白いものが増えた乳母にそっと声をかける。
「ありがとう、時橋」
だが、夢中になって火箸で炭をつついている時橋には聞こえないようだ。
「え、何か仰せになられましたか」
背後を振り返るのに、泉水は微笑んで首を振った。
「いや、何でもない」
「おかしな姫さまでいらっしゃいますこと」
時橋は小首を傾げている。再び背を向けた時橋に、心の中でそっと呼びかけた。
―時橋、いつまでも苦労をかけて済まぬ。
一昨年の秋に榊原邸を突如として出奔して以来、時橋には言うに言えない苦労をかけた。本来なら、泉水が榊原の屋敷を出た今、時橋はここまで付いてくる必要はないのだ。三人の娘たちのいずれかの嫁ぎ先に身を落ち着け、孫の守りをしながら安気に余生を過ごすことができるはずだ。それなのに、こうして泉水の傍につきっきりでいるばかりに、江戸から離れた山の尼寺に暮らし、下女紛いの仕事をして苦労をさせている。
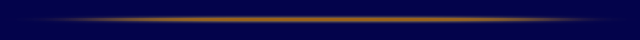
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える