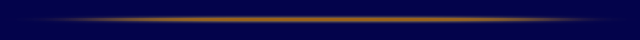
胡蝶の夢~私の最愛~⑪【夢路・ゆめじ】
第8章 予期せぬ災難
でも、何かが違う。
誠吉が嬉しげに口にする〝おさよ〟という名を聞く度、泉水は違和感を憶えるのだ。日に何度となく呼ばれても一向に馴染めない名前は、まるで着慣れぬ着物を身に纏っているようで、しっくりこない。
その時、開け放したままの腰高障子から顔を覗かせた男がいた。
「誠吉、いるか?」
白髪の優しげな老人は、同じ裏店に住む伊東宗竹である。もう六十は近い歳だが、金のない貧乏人から高い施薬料を取らないので、人気があった。腕の方も確かで、若い頃には長崎へ遊学して最新の和蘭医術を会得したという。
「ああ、先生か」
誠吉が立ち上がる。
「どうじゃな、おさよちゃん。具合の方は」
優しく問われ、泉水は微笑んだ。
「相変わらずで、何も思い出せません」
この老医師には泉水は何度も世話になった。宗竹は毎日のように顔を見せ、泉水の様子を確かめる。
「そうじゃ、これを持ってきたぞ」
宗竹に渡されたのは、鉢植えの夕顔であった。白い大輪の花が二つ、蕾が数個ついている。
「綺麗」
泉水が歓声を上げて魅入ると、宗竹は笑った。
「誠吉は、わしを酒飲みの藪医者だと好いるが、これでも取り柄はあるのだぞ」
これには誠吉が笑い声を上げた。
「本当だ、先生、どうせなら、医者よりは花売りにでもなった方が良かったんじゃねえか」
誠吉の言うことも一理あるかもしれない。何しろ、宗竹の住まいの前は、この時季は色とりどりの朝顔や夕顔の鉢が所狭しと並んでいる。宗竹の酒好きと花好きは有名だ。
大方、この夕顔の花も宗竹の丹精したものの一つをお裾分けに持ってきてくれたのだろう。
「まあ、焦りは禁物じゃ。わしの診立てよりも傷の方も軽かったようだし、正直、このように早くに回復するとは思わなかったほどよ。ただ、ここはな」
宗竹は自分の白髪頭を人差し指でチョンチョンとつついた。
誠吉が嬉しげに口にする〝おさよ〟という名を聞く度、泉水は違和感を憶えるのだ。日に何度となく呼ばれても一向に馴染めない名前は、まるで着慣れぬ着物を身に纏っているようで、しっくりこない。
その時、開け放したままの腰高障子から顔を覗かせた男がいた。
「誠吉、いるか?」
白髪の優しげな老人は、同じ裏店に住む伊東宗竹である。もう六十は近い歳だが、金のない貧乏人から高い施薬料を取らないので、人気があった。腕の方も確かで、若い頃には長崎へ遊学して最新の和蘭医術を会得したという。
「ああ、先生か」
誠吉が立ち上がる。
「どうじゃな、おさよちゃん。具合の方は」
優しく問われ、泉水は微笑んだ。
「相変わらずで、何も思い出せません」
この老医師には泉水は何度も世話になった。宗竹は毎日のように顔を見せ、泉水の様子を確かめる。
「そうじゃ、これを持ってきたぞ」
宗竹に渡されたのは、鉢植えの夕顔であった。白い大輪の花が二つ、蕾が数個ついている。
「綺麗」
泉水が歓声を上げて魅入ると、宗竹は笑った。
「誠吉は、わしを酒飲みの藪医者だと好いるが、これでも取り柄はあるのだぞ」
これには誠吉が笑い声を上げた。
「本当だ、先生、どうせなら、医者よりは花売りにでもなった方が良かったんじゃねえか」
誠吉の言うことも一理あるかもしれない。何しろ、宗竹の住まいの前は、この時季は色とりどりの朝顔や夕顔の鉢が所狭しと並んでいる。宗竹の酒好きと花好きは有名だ。
大方、この夕顔の花も宗竹の丹精したものの一つをお裾分けに持ってきてくれたのだろう。
「まあ、焦りは禁物じゃ。わしの診立てよりも傷の方も軽かったようだし、正直、このように早くに回復するとは思わなかったほどよ。ただ、ここはな」
宗竹は自分の白髪頭を人差し指でチョンチョンとつついた。
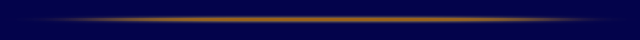
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える