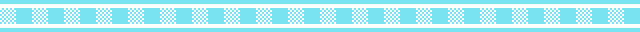
シャイニーストッキング
第14章 もつれるストッキング3 常務取締役大原浩一
100 永岡支社長のしたたかさ
「そんなぁ雪国らしいってぇ、そうなんですぅ、わたし新潟の大学卒なんでぇ、新潟からは一度も出た事がない田舎モノなんですよぉ」
そんな彼女の言葉もまるで…
クラブホステスの会話そのものにしか聞こえない。
いや、クラブホステスそのものである…
「え、大原常務さんは、もちろん東京のご出身でぇ?」
「あ、いや、私め地方の、いや、栃木県出身の田舎モンですよ」
「えぇ、大原常務さんは洗練されてらっしゃるからぁ、そんな地方出身には見えませんでしたぁ」
完全にクラブホステスとの会話みたいになってきた。
そしておそらく、私がそんな思い、違和感を感じている様子が滲み出たのであろう、いや多分、したたかに泳ぐのに長けている永岡支社長が敏感に察知をしたのであろう、すかさず…
「いやぁ、あ、前常務の、いや、真中常務はこの竹下くんの事がお気に入りでしてねぇ…
私がつい、同席させてしまったんですよ」
と、咄嗟に永岡支社長は言ってきたのである。
「あ、それは…
いや、彼女、竹下くんは明るく華があって、私と永岡さんの二人だけでは味気なかっただろうから、かえって良かったですよ」
私は、この場を白けさせない意味でもそう言う、いや、言うしかなかったのだ。
「え、大原常務にそう言ってもらえるとありがたいんですが…
私がつい真中さんとの流れのままで彼女を連れてきてしまって本当に迂闊でした」
さすがこの永岡支社長は、前真中常務の腰巾着の一人である…
瞬時に私の雰囲気を敏感に察知し、すかさず下手に出て、全てを前常務のせいにするという逃げの一手をすかさずしてきたのである。
そしてそれはさっきまでの前常務という呼び方から、真中さんという役職呼称をすかさず外して個人名で呼んだという事にも表れていた…
きっと彼、永岡支社長は、こうして雰囲気や空気を敏感に察知をし、上手く泳いでこの新潟支社長という地位を獲得し、必死に確保していたのであろう…
と、私はこの時思ったのだ。
そしてこの目の前にいるホステス然としての秘書の竹下雪恵という彼女も、彼女なりに必死に振る舞っているのであろう…
そうも思った、いや、思い直したのである。
だってこれが今までの、そして独裁的にこの保険会社を牛耳り君臨していた真中前常務による悪影響といえるから…
「そんなぁ雪国らしいってぇ、そうなんですぅ、わたし新潟の大学卒なんでぇ、新潟からは一度も出た事がない田舎モノなんですよぉ」
そんな彼女の言葉もまるで…
クラブホステスの会話そのものにしか聞こえない。
いや、クラブホステスそのものである…
「え、大原常務さんは、もちろん東京のご出身でぇ?」
「あ、いや、私め地方の、いや、栃木県出身の田舎モンですよ」
「えぇ、大原常務さんは洗練されてらっしゃるからぁ、そんな地方出身には見えませんでしたぁ」
完全にクラブホステスとの会話みたいになってきた。
そしておそらく、私がそんな思い、違和感を感じている様子が滲み出たのであろう、いや多分、したたかに泳ぐのに長けている永岡支社長が敏感に察知をしたのであろう、すかさず…
「いやぁ、あ、前常務の、いや、真中常務はこの竹下くんの事がお気に入りでしてねぇ…
私がつい、同席させてしまったんですよ」
と、咄嗟に永岡支社長は言ってきたのである。
「あ、それは…
いや、彼女、竹下くんは明るく華があって、私と永岡さんの二人だけでは味気なかっただろうから、かえって良かったですよ」
私は、この場を白けさせない意味でもそう言う、いや、言うしかなかったのだ。
「え、大原常務にそう言ってもらえるとありがたいんですが…
私がつい真中さんとの流れのままで彼女を連れてきてしまって本当に迂闊でした」
さすがこの永岡支社長は、前真中常務の腰巾着の一人である…
瞬時に私の雰囲気を敏感に察知し、すかさず下手に出て、全てを前常務のせいにするという逃げの一手をすかさずしてきたのである。
そしてそれはさっきまでの前常務という呼び方から、真中さんという役職呼称をすかさず外して個人名で呼んだという事にも表れていた…
きっと彼、永岡支社長は、こうして雰囲気や空気を敏感に察知をし、上手く泳いでこの新潟支社長という地位を獲得し、必死に確保していたのであろう…
と、私はこの時思ったのだ。
そしてこの目の前にいるホステス然としての秘書の竹下雪恵という彼女も、彼女なりに必死に振る舞っているのであろう…
そうも思った、いや、思い直したのである。
だってこれが今までの、そして独裁的にこの保険会社を牛耳り君臨していた真中前常務による悪影響といえるから…
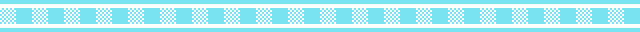
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える