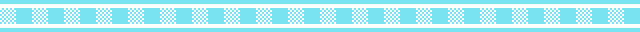
シャイニーストッキング
第14章 もつれるストッキング3 常務取締役大原浩一
99 ホステス然とした…
そもそもが、地方支社の秘書は、いや、イチ地方支社の、新潟支社の業務内容を鑑みても、秘書課としては様々な業務的には必要ではあるのだが…
支社長専属の秘書などはいらない筈なのである。
つまりそれはこの支社長専属秘書というのは名ばかりに過ぎず…
簡単にいえばこうしたVIP待遇のお客様用の接待要員としての存在であるという事なのだろう。
そしてそれは…
『やっぱりぃ、東京の本社の秘書さん達は皆お綺麗な美人さんばかりなんですかぁ?』
『でもぉ、東京にはもっともっと沢山の美人さんがいるだろうしなぁ』
等々の彼女の言葉が証明しているのだ。
綺麗な美人…
つまりそれが支社長専属秘書としての基準であり、存在意義の全てであると。
確かに、この目の前にいるさっきからせっせとビールを注ぎ、料理を小分けして配膳してくれているまるでホステス然とした動きと気配りを見せている彼女の見た目は…
全体的に男心をそそる様な、実年齢にそぐわない感じの艶気と色香を漂わせている、律子とはまた真逆な美人の類の存在感を滲ませてきてはいる。
「わたしなんかぁ、この田舎の新潟から出た事なんてないしぃ…」
「え、あ、そのぉ」
私はそもそもが彼女が永岡支社長との会談に同席しているのも、あくまでもイチ秘書としての存在であると思っていたから…
彼女の名前すら軽く聞き流してしまっていて、記憶にもなかった。
だから私の目が、彼女に問いかけたのであろう?…
「あ、竹下です、竹下雪恵です」
と、彼女は自ら名乗ってくる。
「あ、うん、そうか、そうだった竹下さんだ…」
おそらくは最初に秘書として名乗った筈であろうから、私は咄嗟にそう返し…
「うん、雪恵さんて…さすが雪国新潟らしい美しい名前だなぁ」
そう繕う言葉がスッと出た。
「あら常務さん、そんな美しい名前なんてぇ、嬉しいですわぁ」
「え、あ、うん…」
そして私は、咄嗟に自分の口からそんなベタな言葉が出た事に驚いてしまう。
まさか、そんな言葉が出るなんて…
だが、それ自体も、既に彼女の事を、いや、この秘書の竹下雪恵さんを軽いホステス然として見ている証拠だともいえるであろう。
「雪国らしいってぇ、そうなんですぅ、わたし新潟の大学卒なんでぇ、新潟からは一度も出た事がない田舎モノなんですよぉ」
そもそもが、地方支社の秘書は、いや、イチ地方支社の、新潟支社の業務内容を鑑みても、秘書課としては様々な業務的には必要ではあるのだが…
支社長専属の秘書などはいらない筈なのである。
つまりそれはこの支社長専属秘書というのは名ばかりに過ぎず…
簡単にいえばこうしたVIP待遇のお客様用の接待要員としての存在であるという事なのだろう。
そしてそれは…
『やっぱりぃ、東京の本社の秘書さん達は皆お綺麗な美人さんばかりなんですかぁ?』
『でもぉ、東京にはもっともっと沢山の美人さんがいるだろうしなぁ』
等々の彼女の言葉が証明しているのだ。
綺麗な美人…
つまりそれが支社長専属秘書としての基準であり、存在意義の全てであると。
確かに、この目の前にいるさっきからせっせとビールを注ぎ、料理を小分けして配膳してくれているまるでホステス然とした動きと気配りを見せている彼女の見た目は…
全体的に男心をそそる様な、実年齢にそぐわない感じの艶気と色香を漂わせている、律子とはまた真逆な美人の類の存在感を滲ませてきてはいる。
「わたしなんかぁ、この田舎の新潟から出た事なんてないしぃ…」
「え、あ、そのぉ」
私はそもそもが彼女が永岡支社長との会談に同席しているのも、あくまでもイチ秘書としての存在であると思っていたから…
彼女の名前すら軽く聞き流してしまっていて、記憶にもなかった。
だから私の目が、彼女に問いかけたのであろう?…
「あ、竹下です、竹下雪恵です」
と、彼女は自ら名乗ってくる。
「あ、うん、そうか、そうだった竹下さんだ…」
おそらくは最初に秘書として名乗った筈であろうから、私は咄嗟にそう返し…
「うん、雪恵さんて…さすが雪国新潟らしい美しい名前だなぁ」
そう繕う言葉がスッと出た。
「あら常務さん、そんな美しい名前なんてぇ、嬉しいですわぁ」
「え、あ、うん…」
そして私は、咄嗟に自分の口からそんなベタな言葉が出た事に驚いてしまう。
まさか、そんな言葉が出るなんて…
だが、それ自体も、既に彼女の事を、いや、この秘書の竹下雪恵さんを軽いホステス然として見ている証拠だともいえるであろう。
「雪国らしいってぇ、そうなんですぅ、わたし新潟の大学卒なんでぇ、新潟からは一度も出た事がない田舎モノなんですよぉ」
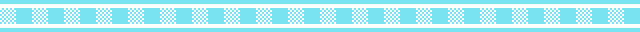
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える