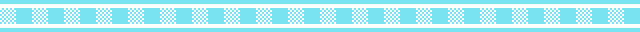
ぜんぶ俺の物〜ケダモノ弟の危険な独占欲〜
第1章 1
「亜貴がねえ、独立してこっちで店を開くっていうのよ」
気まずい沈黙に押しつぶされながらなんとか辿り着いた実家の食卓で、私はビールを噴き出しそうになった。
「はあ!?」
どういうこと?
東京で働いてるんじゃないの?
こっちで店を開くって……もしかして、亜貴まで地元(こっち)に戻ってくるってこと?
「名目上は独立ってだけで、実際は本社のフランチャイズ。こっちなら知り合いも多いしさ」
絆創膏を貼った長い指で、亜貴はもくもくとパスタを口に運んでいる。
「昨年からそういう話があったみたいなんだけどねえ、聞かされた方は突然だから驚きよ」
最近の美容業界では、独立を希望する社員にのれん分けする流れが多いのだとか。企業側も手塩にかけて育ててきた技術力を手放さなくて済むし、オーナー側も、出品コストを抑えられるうえ、サポート体制も万全。まさにウインウインな関係なのだそうだ。
でも何で突然、独立なんかする気になったのだろう。しかも、どうして東京じゃなく地元で開業しようと思ったのだろう。
まさか、私が結婚して地元に戻ってきたせい? と考えるのは、自意識過剰すぎるだろうか。
私はちらりと視線を上げて、亜貴の様子を伺う。実家に戻ってきてから、まだ一度も目が合っていない。
相変わらず、まつ毛が長いなあ。
亜貴は、男にしては色白な方なんだろうな。
黙々とキノコパスタを口に運びながら、私はそれとなく亜貴の観察を続ける。
美容にも気を遣っているのか、以前にもまして肌艶が良い。
細長い指。ほどよくしなやかな骨格に、透き通って張りのある声。
女の子はみんな、奇麗なものが好きだ。
色どり鮮やかに盛り付けられたお料理に、かわいいお店。カリスマ店員に読者モデル。まるで甘い蜜の香りに引き寄せられる蝶みたいに、女の子は奇麗なものばかりに群がろうとする。
そんな彼女たちに、亜貴は愛されてきたのだろう。
「ん?」
亜貴の目が突然私に向いたので、慌てて視線をお皿に戻す。
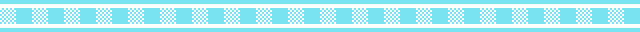
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える