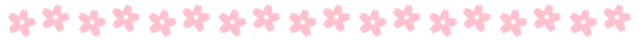
氷華~恋は駆け落ちから始まって~
第3章 幻の村
天幕にいたのは寝込んでから数日間だけで、家が完成するなり、トンジュはサヨンを家に移した。高熱を発している身体に、夜露が十分に凌げない天幕はふさわしくないと判断し、自分は寝食の時間を削ってでも家の完成を優先させたのだった。
寝込んで十一日め、サヨンはやっと熱も下がり、外に出ることができた。
トンジュはまだ家で寝ていろと煩いのだけれけど、サヨンが勝手に動き回っているのだ。
サヨンが回復すると、トンジュは毎日、出かけるようになった。大抵は森に出て、薬草を採ったり、狩りをしたりする。朝早く出かけ、陽暮れ刻に帰ってくるのが常だった。
鹿肉や兎肉、猪肉はその日の夕飯の何よりのご馳走になった。サヨンは実を言うとー、あまり料理が得意ではない。しかし、トンジュはサヨンが拵えるどんな料理でも―もし、それが料理と呼べる代物であればの話だが―、歓んで食べた。
サヨンの手にかかると、折角のご馳走になるはずの食材が台無しになってしまう。トンジュは黒こげになった肉のかたまりを見ても、ただ笑っているだけだ。
「ごめんなさい」
しゅんとして肩を落とすサヨンの頭をくしゃくしゃと撫で、水で炭のような肉塊をようよう飲み下している。
あまりにそんなことが続くので、ついにはトンジュが自分で料理の腕をふるうようになった。
彼の腕の方がよほどサヨンよりも上だ。その事実に、サヨンは大いに傷ついた。
「私ってば、本当に何もできない役立たずね」
溜息をついて落ち込んでいると、トンジュが微笑んだ。
「これからゆっくり憶えていけば良いですよ。サヨンさまなら、何だって、すぐに憶えてできるようになりますから」
慰めとも励ましとも取れる言葉をくれる。
この頃のトンジュは凪いだ湖のように穏やかで、サヨンを温かく見守ってくれる。サヨンに対する態度は異性というよりも兄が妹に示す親愛の情に近かった。
サヨンは思った。
もしかしたら、このまま自分たちは今の心地よい関係を続けてゆけるのではないか。
男だとか女だとかの区別なく、異性だという意識を持たず、人生の協力者、或いは友達のような関係を作り上げてゆけるかもしれない。
かすかな希望が見え始めていた。
寝込んで十一日め、サヨンはやっと熱も下がり、外に出ることができた。
トンジュはまだ家で寝ていろと煩いのだけれけど、サヨンが勝手に動き回っているのだ。
サヨンが回復すると、トンジュは毎日、出かけるようになった。大抵は森に出て、薬草を採ったり、狩りをしたりする。朝早く出かけ、陽暮れ刻に帰ってくるのが常だった。
鹿肉や兎肉、猪肉はその日の夕飯の何よりのご馳走になった。サヨンは実を言うとー、あまり料理が得意ではない。しかし、トンジュはサヨンが拵えるどんな料理でも―もし、それが料理と呼べる代物であればの話だが―、歓んで食べた。
サヨンの手にかかると、折角のご馳走になるはずの食材が台無しになってしまう。トンジュは黒こげになった肉のかたまりを見ても、ただ笑っているだけだ。
「ごめんなさい」
しゅんとして肩を落とすサヨンの頭をくしゃくしゃと撫で、水で炭のような肉塊をようよう飲み下している。
あまりにそんなことが続くので、ついにはトンジュが自分で料理の腕をふるうようになった。
彼の腕の方がよほどサヨンよりも上だ。その事実に、サヨンは大いに傷ついた。
「私ってば、本当に何もできない役立たずね」
溜息をついて落ち込んでいると、トンジュが微笑んだ。
「これからゆっくり憶えていけば良いですよ。サヨンさまなら、何だって、すぐに憶えてできるようになりますから」
慰めとも励ましとも取れる言葉をくれる。
この頃のトンジュは凪いだ湖のように穏やかで、サヨンを温かく見守ってくれる。サヨンに対する態度は異性というよりも兄が妹に示す親愛の情に近かった。
サヨンは思った。
もしかしたら、このまま自分たちは今の心地よい関係を続けてゆけるのではないか。
男だとか女だとかの区別なく、異性だという意識を持たず、人生の協力者、或いは友達のような関係を作り上げてゆけるかもしれない。
かすかな希望が見え始めていた。
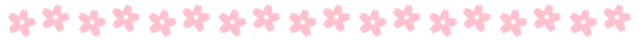
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える