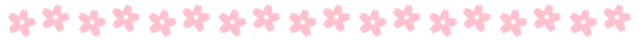
氷華~恋は駆け落ちから始まって~
第3章 幻の村
ゆえに、厳密にいえば、サヨンがトンジュを知っているのは十歳以降の彼だ。だからこそ、サヨンもあのときの泣いていた子どもがトンジュだとは気づかなかった。
「あのときから、俺は夢を見るようになったんです」
トンジュが懐から後生大切そうに取り出したのは、小さな髪飾りだった。
「これに見憶えがありますか?」
サヨンは差し出されたリボンを受け取った。半ば色褪せた子ども用の髪飾りは、昔は確かに鮮やかな牡丹色をしていたのだろうと彷彿させる。
「忘れるはずもないわ。私が使っていた髪飾りよ。私があの時、泣いていたあなたの手に巻いたものでしょう」
「俺にとって、これはずっと宝物でした。辛い時悔しい時、いつもこれを眺めていたんです。今日、哀しいことがあったのだから、明日は必ず良いことがあると言ってくれたサヨンさまの言葉を噛みしめながら生きてきました」
わずかな沈黙があった。新たにくべられた薪が勢いよく燃え上がった。
「あの日、俺はお嬢さまを妻にするんだ、あの優しくて賢い女の子をいつか手に入れたいと子ども心に決意したんです。あのときから、俺はずっとサヨンさまだけを見つめてきました」
焔を宿したトンジュの瞳は、彼自身の瞳の底で焔が揺らめいているように見えた。その燃えるような烈しいまなざしでひたと見つめられ、サヨンは居たたまれなくなった。
トンジュのたったひと言で、あのときの少年との〝再会〟の歓びも一瞬でしぼんだ。
今や懐かしさよりも当惑の方が強かった。
トンジュの気持ちは、あまりに重すぎる。〝好きだ、惚れている〟と何千回耳許で繰り返されても、今のサヨンにはただ重荷になるだけだった。
トンジュを嫌いというわけではない。しかし、ソン・トンジュという男は、自分の欲しいものを手に入れるためには、どこまでも計算高く冷徹になれる。
しかも、つい今し方、トンジュはこれまでの紳士的然とした態度を豹変させ、サヨンに飢えた獣のように襲いかかってきたのだ。サヨンがどんなに泣き叫んで懇願しても、途中で止めてはくれなかった。
もし、脚の痛みがぶり返さなかったら、今頃、自分はどうなっていたことか。その先を考えただけで、怖ろしさに気を失いそうになった。
「あのときから、俺は夢を見るようになったんです」
トンジュが懐から後生大切そうに取り出したのは、小さな髪飾りだった。
「これに見憶えがありますか?」
サヨンは差し出されたリボンを受け取った。半ば色褪せた子ども用の髪飾りは、昔は確かに鮮やかな牡丹色をしていたのだろうと彷彿させる。
「忘れるはずもないわ。私が使っていた髪飾りよ。私があの時、泣いていたあなたの手に巻いたものでしょう」
「俺にとって、これはずっと宝物でした。辛い時悔しい時、いつもこれを眺めていたんです。今日、哀しいことがあったのだから、明日は必ず良いことがあると言ってくれたサヨンさまの言葉を噛みしめながら生きてきました」
わずかな沈黙があった。新たにくべられた薪が勢いよく燃え上がった。
「あの日、俺はお嬢さまを妻にするんだ、あの優しくて賢い女の子をいつか手に入れたいと子ども心に決意したんです。あのときから、俺はずっとサヨンさまだけを見つめてきました」
焔を宿したトンジュの瞳は、彼自身の瞳の底で焔が揺らめいているように見えた。その燃えるような烈しいまなざしでひたと見つめられ、サヨンは居たたまれなくなった。
トンジュのたったひと言で、あのときの少年との〝再会〟の歓びも一瞬でしぼんだ。
今や懐かしさよりも当惑の方が強かった。
トンジュの気持ちは、あまりに重すぎる。〝好きだ、惚れている〟と何千回耳許で繰り返されても、今のサヨンにはただ重荷になるだけだった。
トンジュを嫌いというわけではない。しかし、ソン・トンジュという男は、自分の欲しいものを手に入れるためには、どこまでも計算高く冷徹になれる。
しかも、つい今し方、トンジュはこれまでの紳士的然とした態度を豹変させ、サヨンに飢えた獣のように襲いかかってきたのだ。サヨンがどんなに泣き叫んで懇願しても、途中で止めてはくれなかった。
もし、脚の痛みがぶり返さなかったら、今頃、自分はどうなっていたことか。その先を考えただけで、怖ろしさに気を失いそうになった。
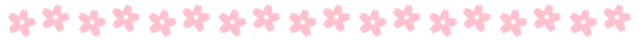
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える