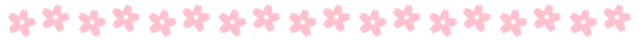
氷華~恋は駆け落ちから始まって~
第3章 幻の村
わずか七歳の子どもが自分から身を売ったのである。トンジュは元々は良民の身分を持っていたのに、そのときから隷民になったのだ。身を売って得たなけなしの金は、町外れの寺に喜捨してきた。寺の住職に金を渡し、ろくな供養もして貰えず亡くなった村人たちのために経をあげて欲しいと頭を下げて頼んだ。
幸い住職が慈悲深い人だったため、トンジュは安心して町を離れることができた。彼は奴隷商人と共に旅を続け、無事、漢陽に着いた。奴隷商人がトンジュを連れていった奉公先というのが他ならぬコ・ヨンセの屋敷であったというわけだ。
「今でこそ図体だけはでかくなったけど、俺はガキの時分はチビでした」
トンジュの言葉に、サヨンは笑った。
「よく憶えてるわよ。あの頃は、まだ私の方が背が高かったんだもの」
「だからかな、よく他の下男連中から苛められたんです。旦那さまに学問を教えて頂いていることを知っていたのは朴(パク)執事さまと女中頭さまだけだったので、そのことが原因ではなかったと思うのですが、とにかく生意気だとか何とか、理由にもならない理由で泣かされてばかりでした」
そんなある日、幼いトンジュは井戸端で泣いていた。既に夜毎、大行首の部屋へ伺って学問の稽古をつけて貰うのは日課になっていた頃の話だ。
泣きじゃくるトンジュの小さな手には、大行首さまから頂いた大切な書物が握りしめられていた。それは子ども向けのハングル語初心者用教本であった。頂いてからひと月を経ない中に、その薄い本は幾度も読み返され、自分で書き足した跡や大行首さまから聞いた大切なことが走り書きで記されていた。
その大切な本をあろうことか、年上の下男に取り上げられ、何枚かを破られてしまったのだ。トンジュは哀しいことがあった時、井戸端でよくひっそりと泣いた。ここならば、人眼につかず、泣きたいだけ泣けるからだ。
そのときも本を胸に抱いて声を上げて泣いていたのだが、不運にも通りすがりの誰かがトンジュを見つけてしまったのだった。
―泣かないで。
泣いている幼いトンジュの肩にそっと置かれた小さな手の温もり。
そのときの記憶は、七歳の多感な少年の記憶に鮮烈な印象を残した。
幸い住職が慈悲深い人だったため、トンジュは安心して町を離れることができた。彼は奴隷商人と共に旅を続け、無事、漢陽に着いた。奴隷商人がトンジュを連れていった奉公先というのが他ならぬコ・ヨンセの屋敷であったというわけだ。
「今でこそ図体だけはでかくなったけど、俺はガキの時分はチビでした」
トンジュの言葉に、サヨンは笑った。
「よく憶えてるわよ。あの頃は、まだ私の方が背が高かったんだもの」
「だからかな、よく他の下男連中から苛められたんです。旦那さまに学問を教えて頂いていることを知っていたのは朴(パク)執事さまと女中頭さまだけだったので、そのことが原因ではなかったと思うのですが、とにかく生意気だとか何とか、理由にもならない理由で泣かされてばかりでした」
そんなある日、幼いトンジュは井戸端で泣いていた。既に夜毎、大行首の部屋へ伺って学問の稽古をつけて貰うのは日課になっていた頃の話だ。
泣きじゃくるトンジュの小さな手には、大行首さまから頂いた大切な書物が握りしめられていた。それは子ども向けのハングル語初心者用教本であった。頂いてからひと月を経ない中に、その薄い本は幾度も読み返され、自分で書き足した跡や大行首さまから聞いた大切なことが走り書きで記されていた。
その大切な本をあろうことか、年上の下男に取り上げられ、何枚かを破られてしまったのだ。トンジュは哀しいことがあった時、井戸端でよくひっそりと泣いた。ここならば、人眼につかず、泣きたいだけ泣けるからだ。
そのときも本を胸に抱いて声を上げて泣いていたのだが、不運にも通りすがりの誰かがトンジュを見つけてしまったのだった。
―泣かないで。
泣いている幼いトンジュの肩にそっと置かれた小さな手の温もり。
そのときの記憶は、七歳の多感な少年の記憶に鮮烈な印象を残した。
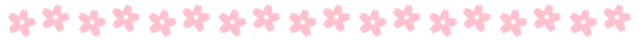
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える