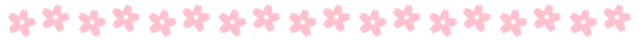
氷華~恋は駆け落ちから始まって~
第3章 幻の村
そこはサヨンなどが迂闊に入り込んではならない彼の心の聖域のように思えたのである。
サヨンが物想いに耽っている間にも、トンジュの述懐は続いていった。
「あれは、俺が七つの誕生日を迎える直前でした。祖母から都に行けと勧められたんです」
「あなたのお祖母(ばあ)さまは、どうしてそんなことを?」
「この村にいたら、死ななければならなくなるから」
トンジュの口から、村滅亡の核心に触れそうな話が出て、サヨンは息を呑んだ。
「でも、何故、そうなってしまうの?」
トンジュが村の話を語り始めて、初めてサヨンを真正面から見た。
「流行病(はやりやまい)が村を襲ったのです。手の打ちようがなかった。それほどの大被害でした。まず年寄りや幼い子ども、弱い者たちから次々に倒れてゆき、気がついてみたら、元々少なかった村人の数は数えるほどになっていた」
「村の人たちは町の名医でも太刀打ちできないほどの薬草の知識を持っていたのに、その知識をうまく活用できなかったのかしら」
「駄目でしたね。あの流行病は質が悪すぎた。仮にあの病に効く薬草を知っている人がいたとしても、既に薬草を探しにゆくだけの体力がなかったのかもしれない」
「では、結局、村の人たちは流行病で死に絶えてしまったということ?」
〝いいえ〟と、トンジュは首を振った。
「ある日、地方役所の役人たちがどかどかとやって来て、この村を焼き払ったんです」
「―そんな、酷い、酷いことって」
サヨンの薄紅色の唇が戦慄いた。
「放っておいても、村は遠からず自滅したでしょう。何しろ下界とここは見えない帳で分断されているようなものだ。麓の人間は、村人の導きがなければ、けして村までは辿り着けないし、刻が経ってしまえば、ここの人々は一人残らずその流行病で亡くなっていたはずです。それだけ完璧に隔絶され、行き来がないのだから、病が麓の町や村までひろがる可能性は断じてなかった」
「トンジュ、麓の人だけではここまで来られなかったのなら、どのような手を使って、役人は村を焼き払いにきたの?」
トンジュが淋しげな微笑を浮かべた。
サヨンが物想いに耽っている間にも、トンジュの述懐は続いていった。
「あれは、俺が七つの誕生日を迎える直前でした。祖母から都に行けと勧められたんです」
「あなたのお祖母(ばあ)さまは、どうしてそんなことを?」
「この村にいたら、死ななければならなくなるから」
トンジュの口から、村滅亡の核心に触れそうな話が出て、サヨンは息を呑んだ。
「でも、何故、そうなってしまうの?」
トンジュが村の話を語り始めて、初めてサヨンを真正面から見た。
「流行病(はやりやまい)が村を襲ったのです。手の打ちようがなかった。それほどの大被害でした。まず年寄りや幼い子ども、弱い者たちから次々に倒れてゆき、気がついてみたら、元々少なかった村人の数は数えるほどになっていた」
「村の人たちは町の名医でも太刀打ちできないほどの薬草の知識を持っていたのに、その知識をうまく活用できなかったのかしら」
「駄目でしたね。あの流行病は質が悪すぎた。仮にあの病に効く薬草を知っている人がいたとしても、既に薬草を探しにゆくだけの体力がなかったのかもしれない」
「では、結局、村の人たちは流行病で死に絶えてしまったということ?」
〝いいえ〟と、トンジュは首を振った。
「ある日、地方役所の役人たちがどかどかとやって来て、この村を焼き払ったんです」
「―そんな、酷い、酷いことって」
サヨンの薄紅色の唇が戦慄いた。
「放っておいても、村は遠からず自滅したでしょう。何しろ下界とここは見えない帳で分断されているようなものだ。麓の人間は、村人の導きがなければ、けして村までは辿り着けないし、刻が経ってしまえば、ここの人々は一人残らずその流行病で亡くなっていたはずです。それだけ完璧に隔絶され、行き来がないのだから、病が麓の町や村までひろがる可能性は断じてなかった」
「トンジュ、麓の人だけではここまで来られなかったのなら、どのような手を使って、役人は村を焼き払いにきたの?」
トンジュが淋しげな微笑を浮かべた。
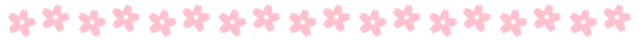
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える