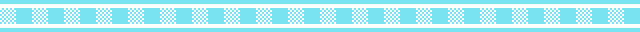
20年 あなたと歩いた時間
第12章 君が生きた日々
二学期が始まった。
まだまだ体は本調子ではないけれど、
取りあえずは死にたいとか考えなくなった。
昨日、のぞみが大学の看護学部に推薦が
決まった。
たぶん、高校3年の一学期までの成績が、ほぼ
オール5でないと取れないような推薦だ。
そんなすごい推薦に、のぞみが決まった。
あいつ、どんだけ成績良かったんだ?
中学の時、苦労して不規則動詞を覚えていた
のぞみが。
でもそのことで僕は、本気で京都医大に行く
気が固まった。
合格したら、またのぞみと一緒だ。
その時、電話が鳴った。
「…もしもし、小野塚です」
『…あっ、流星?私、真緒』
真緒。めずらしい。
最近要から僕のことを聞いてか聞かずか、
それとも昔からなのか僕への風当たりが
きつい。
『ごめん、のぞみが熱出したらしくて、私に電話あったんだけど私今から塾でさ。のぞみのパパ、今日学会で泊まりなんだ。ねえ、流星ちょっと見てきて?なんやかんやであんたしかいないんだわ』
「…消去法でおれかよ」
『あったりまえでしょ?!前科一犯も二犯もあるやつにのぞみを任せられるかっつの!』
「は…ひでーな、おまえ」
『めちゃくちゃしんどそうだったから、なんかゼリーとか買って。あ、授業始まるから!頼んだよ!へんなことしないでよ!』
「ば、するかよ…おれは…」
電話は切れていた。
のぞみ、昨日は元気だったのに。気がつくと
僕は家の冷凍庫にあったアイスノンと、
『さとみ』と書かれたアイスクリームを
自転車のかごに突っ込んでいた。
いつの間にか、だるさはなくなり、痩せた体が
フットワークを軽くさせていた。
「流星…なんで」
玄関を開けたのぞみは、ドアに寄りかかる
ようにして立っていた。
「真緒から電話あって、のぞみんとこに行ってくれって…いや、もちろんおれが来たかったんだけどっ」
うしろめたさが、変な言い訳を言わせた。
のぞみは熱が高いのか、真っ赤な顔を
していた。
まだまだ体は本調子ではないけれど、
取りあえずは死にたいとか考えなくなった。
昨日、のぞみが大学の看護学部に推薦が
決まった。
たぶん、高校3年の一学期までの成績が、ほぼ
オール5でないと取れないような推薦だ。
そんなすごい推薦に、のぞみが決まった。
あいつ、どんだけ成績良かったんだ?
中学の時、苦労して不規則動詞を覚えていた
のぞみが。
でもそのことで僕は、本気で京都医大に行く
気が固まった。
合格したら、またのぞみと一緒だ。
その時、電話が鳴った。
「…もしもし、小野塚です」
『…あっ、流星?私、真緒』
真緒。めずらしい。
最近要から僕のことを聞いてか聞かずか、
それとも昔からなのか僕への風当たりが
きつい。
『ごめん、のぞみが熱出したらしくて、私に電話あったんだけど私今から塾でさ。のぞみのパパ、今日学会で泊まりなんだ。ねえ、流星ちょっと見てきて?なんやかんやであんたしかいないんだわ』
「…消去法でおれかよ」
『あったりまえでしょ?!前科一犯も二犯もあるやつにのぞみを任せられるかっつの!』
「は…ひでーな、おまえ」
『めちゃくちゃしんどそうだったから、なんかゼリーとか買って。あ、授業始まるから!頼んだよ!へんなことしないでよ!』
「ば、するかよ…おれは…」
電話は切れていた。
のぞみ、昨日は元気だったのに。気がつくと
僕は家の冷凍庫にあったアイスノンと、
『さとみ』と書かれたアイスクリームを
自転車のかごに突っ込んでいた。
いつの間にか、だるさはなくなり、痩せた体が
フットワークを軽くさせていた。
「流星…なんで」
玄関を開けたのぞみは、ドアに寄りかかる
ようにして立っていた。
「真緒から電話あって、のぞみんとこに行ってくれって…いや、もちろんおれが来たかったんだけどっ」
うしろめたさが、変な言い訳を言わせた。
のぞみは熱が高いのか、真っ赤な顔を
していた。
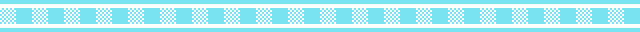
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える