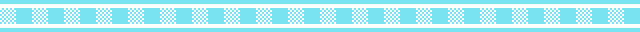
どらくえ3
第3章 ナジミの塔
少し打ち解けた俺達はムタイが眠っているのでそばに座って休むことにした。
リサも元気そうだが、魔法を使って消耗しているはずだった。
各々水を飲んだり、顔を拭いたりして一息つく。
「自己紹介がまだだったね。私はリサ。こっちはムタイ。私のおじいちゃん」
リサが髪を結わえ直して話しかけてきた。
「俺はアベルで、こっちはイース。さっきは悪かった。」
「ううん。こちらこそゴメン。スイッチ入ると止まらないの」
―スイッチ入るとって魔法のこと?それとも口喧嘩のことか?…まあ流して聞いておこう。
「二人で旅してるのか?」
「ええ。アリアハンを出て故郷に帰りたいの。」
「そうなのか。俺達もアリアハンから出るつもりなんだ。魔王退治に。」
リサはアベルの顔を見直して、驚いた顔をしている。
「それ…マジ?」
「大マジ。おかしいか?」
リサはぶんぶんと首を振った。
「おかしくなんかない。やるね。」
そう言ってにっこり笑った。
「じゃあ目的は同じだね。この塔にある盗賊の鍵を探しにきたんでしょ?」
「盗賊の鍵?いや、この塔にいるじいさんに会いにきたんだ。アリアハンから出るための方法を知ってるらしい」
「おじいさん?ふ~ん…よくわかんないけど、そのおじいさんが盗賊の鍵を持ってるのかも。」
「盗賊の鍵って?」
「簡単な扉なら自由に開けられる鍵らしいよ?」
「へー。何で鍵がいるんだ?」
「レーベ村の長老がね、盗賊の鍵があれば魔法の玉を渡すっていうの。旅の泉の封印を解くのに必要なんだって。」
「旅の泉って船を使わずに遠くにいけるんだったな。ていうか、よく知ってるな?」
「だってアリアハンから出るためにムタイと一緒にいろいろ調べたもの。苦労したんだから。」
「そっか」
うん、と頷いてリサはムタイの顔を見た。
ムタイはまだまぶたを閉じている。
その顔はよく日に焼けている。
二人旅の大変さは、俺にもよくわかった。
ましてや女の子と老人ではいくら魔法が使えると言っても、体力的には俺達よりも数倍厳しいはずだと想像できた。
「…一緒に行かないか?」
俺はそうリサに言ってみた。
リサも元気そうだが、魔法を使って消耗しているはずだった。
各々水を飲んだり、顔を拭いたりして一息つく。
「自己紹介がまだだったね。私はリサ。こっちはムタイ。私のおじいちゃん」
リサが髪を結わえ直して話しかけてきた。
「俺はアベルで、こっちはイース。さっきは悪かった。」
「ううん。こちらこそゴメン。スイッチ入ると止まらないの」
―スイッチ入るとって魔法のこと?それとも口喧嘩のことか?…まあ流して聞いておこう。
「二人で旅してるのか?」
「ええ。アリアハンを出て故郷に帰りたいの。」
「そうなのか。俺達もアリアハンから出るつもりなんだ。魔王退治に。」
リサはアベルの顔を見直して、驚いた顔をしている。
「それ…マジ?」
「大マジ。おかしいか?」
リサはぶんぶんと首を振った。
「おかしくなんかない。やるね。」
そう言ってにっこり笑った。
「じゃあ目的は同じだね。この塔にある盗賊の鍵を探しにきたんでしょ?」
「盗賊の鍵?いや、この塔にいるじいさんに会いにきたんだ。アリアハンから出るための方法を知ってるらしい」
「おじいさん?ふ~ん…よくわかんないけど、そのおじいさんが盗賊の鍵を持ってるのかも。」
「盗賊の鍵って?」
「簡単な扉なら自由に開けられる鍵らしいよ?」
「へー。何で鍵がいるんだ?」
「レーベ村の長老がね、盗賊の鍵があれば魔法の玉を渡すっていうの。旅の泉の封印を解くのに必要なんだって。」
「旅の泉って船を使わずに遠くにいけるんだったな。ていうか、よく知ってるな?」
「だってアリアハンから出るためにムタイと一緒にいろいろ調べたもの。苦労したんだから。」
「そっか」
うん、と頷いてリサはムタイの顔を見た。
ムタイはまだまぶたを閉じている。
その顔はよく日に焼けている。
二人旅の大変さは、俺にもよくわかった。
ましてや女の子と老人ではいくら魔法が使えると言っても、体力的には俺達よりも数倍厳しいはずだと想像できた。
「…一緒に行かないか?」
俺はそうリサに言ってみた。
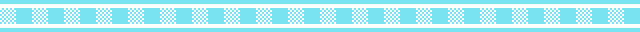
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える