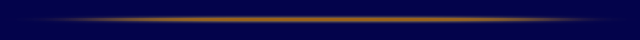
胡蝶の夢~私の最愛~⑪【夢路・ゆめじ】
第30章 花惑い
《巻の壱―花惑い―》
ゆるりと視線を巡らせると、空の蒼さが眼に滲みた。どこまでも際限なく続く蒼穹を眺めていると、刻(とき)の経つのさえ忘れてしまう。この涯(はて)なき空は、どこまで続いているのだろうか。かつて五年という年月を過ごした山の上の尼寺まで、この空は続いているのかと思えば、懐かしさが胸に押し寄せ、溢れてくる。
山頂の庵より更に高く高く、空のはるか彼方には御仏のおわず極楽浄土があるに相違ない。そこにゆけば、時橋にも逢えるだろうか。
泉水が生まれた落ちたその日から、終始影のように付き従い、まめやかに仕えてきた乳母だった。もう、あの優しい乳母は、この世のどこを探してもいない。泉水が剃髪して世捨て人となってしまったことを嘆き、絶望して自ら生命を絶ってしまった。
今頃、時橋は、その浄土とやらの蓮のうてなにいるに違いない。時には厳しく時には優しく、泉水を育て導いてくれた女(ひと)だった。五歳で生母を喪った泉水にとって、時橋は〝母〟と呼ぶ大切な存在であり、唯一、心を許せ信頼できる者であった。
時橋をむざと死なせてしまったという悔恨の念はいまだに泉水をじわじわと責め苛んでいる。
―帰りたい。
泉水は心の中で呟いてみた。だが、我が身が今、いずこに帰りたいと願っているのか、泉水自身ですら判らないのだった。師のような徳高き尼君になりたいと一途に念じ、仏道に精進し続けたあの山寺にか、それとも、時橋のいる浄土なのか。いっそのこと、時橋の許にゆけば、どれほど楽になれるだろう。こうして生きているのか死んでいるのかさえ判らぬ無為の日々を過ごす必要もなく、この世のすべての苦しみから解き放たれる。
だが、今の泉水には、死すら許されない。
―私は死を望むことさえ我が意のままにはならぬのか。
そう思えば、口惜しさと無念が胸の奥で渦巻く。
かつての良人榊原泰雅の命で、まるで略奪されるかのように尼寺から屋敷に連れ戻されたのが数日前のこと。もとより、言い尽くせぬ恩を受けた師匠光照のため、あの月照庵を守るためならば、この身がどうなろうとは厭いはせぬと、覚悟を定めて山を下りた。
いざとなれば、泰雅に触れられる前に、この喉をかききり、女の意地を見せてやるのだと思っていた。しかし。
ゆるりと視線を巡らせると、空の蒼さが眼に滲みた。どこまでも際限なく続く蒼穹を眺めていると、刻(とき)の経つのさえ忘れてしまう。この涯(はて)なき空は、どこまで続いているのだろうか。かつて五年という年月を過ごした山の上の尼寺まで、この空は続いているのかと思えば、懐かしさが胸に押し寄せ、溢れてくる。
山頂の庵より更に高く高く、空のはるか彼方には御仏のおわず極楽浄土があるに相違ない。そこにゆけば、時橋にも逢えるだろうか。
泉水が生まれた落ちたその日から、終始影のように付き従い、まめやかに仕えてきた乳母だった。もう、あの優しい乳母は、この世のどこを探してもいない。泉水が剃髪して世捨て人となってしまったことを嘆き、絶望して自ら生命を絶ってしまった。
今頃、時橋は、その浄土とやらの蓮のうてなにいるに違いない。時には厳しく時には優しく、泉水を育て導いてくれた女(ひと)だった。五歳で生母を喪った泉水にとって、時橋は〝母〟と呼ぶ大切な存在であり、唯一、心を許せ信頼できる者であった。
時橋をむざと死なせてしまったという悔恨の念はいまだに泉水をじわじわと責め苛んでいる。
―帰りたい。
泉水は心の中で呟いてみた。だが、我が身が今、いずこに帰りたいと願っているのか、泉水自身ですら判らないのだった。師のような徳高き尼君になりたいと一途に念じ、仏道に精進し続けたあの山寺にか、それとも、時橋のいる浄土なのか。いっそのこと、時橋の許にゆけば、どれほど楽になれるだろう。こうして生きているのか死んでいるのかさえ判らぬ無為の日々を過ごす必要もなく、この世のすべての苦しみから解き放たれる。
だが、今の泉水には、死すら許されない。
―私は死を望むことさえ我が意のままにはならぬのか。
そう思えば、口惜しさと無念が胸の奥で渦巻く。
かつての良人榊原泰雅の命で、まるで略奪されるかのように尼寺から屋敷に連れ戻されたのが数日前のこと。もとより、言い尽くせぬ恩を受けた師匠光照のため、あの月照庵を守るためならば、この身がどうなろうとは厭いはせぬと、覚悟を定めて山を下りた。
いざとなれば、泰雅に触れられる前に、この喉をかききり、女の意地を見せてやるのだと思っていた。しかし。
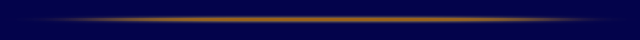
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える