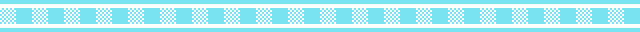
シャイニーストッキング
第7章 絡まるストッキング6 和哉と美冴2
79 嗜好の理解
美冴さんはこの僕の激情とも云える激流の熱いキスの想いが伝わったのか、まるで力が抜けたかの様に脱力し、カラダを僕に預けてきたのだ。
そして僕は美冴さんを強く抱き締めていく。
唇を外し、耳元からうなじへと這わせていくと、更に鼻腔にムスク系の甘い香りが広がり、心を昂ぶらせてくるのだ。
右手ではストッキング脚の爪先を弄り、左手で美冴さんの肩を抱く。
僕の左腕には、痩せた、華奢な美冴さんのカラダを感じていた。
あの頃より少し痩せたんじゃないかな…
そんな感覚が左腕に伝わってくる。
そして僕は一気に顔を下げ、スカートから露わになっている太腿に頬ずりするかの様に顔を押し付けていく。
太腿のピンと張ったストッキングのナイロン繊維が、ザラザラと僕の押し付けた頬を刺激してきていた。
ああ、これだ、これだよ、このストッキングの感触と、甘い香りだよ…
僕には堪らない香りと感触なのである。
そして僕は顔を太腿からゆっくりと下ろしていき、膝、すね、脚首、そして爪先へと伝わせていくのだ。
漂ってくるムスク系の甘い香りに、心がすっかり酔い痴れていた。
そして僕は顔を、いよいよ、五年間の憧れの、渇望し、羨望していたストッキングの爪先へと這わせていく。
美冴さんが失踪的に消えた後、朱美さんに約1年間お世話になり、女性の奥深さを教えて貰った。
だが、僕には、女性の神秘も大切ではあったのだが美冴さん亡き後にも心から切望し、渇望していたのはストッキングラブという、性的嗜好の満足と充足なのであったのだ。
だが、美冴さん以外からはそんな性的嗜好の羨望は、全くといっていい程に満たされはしなかったのである。
朱美さんは比較的脂性で汗かきであったらしく、脚の、ストッキングの爪先の匂いは激臭であったのだ。
そして朱美さんと同時に付き合いを始めた同級生の女子高生はストッキングイコールオバさんの穿くモノ…
というイメージを持っていて、全く持ってストッキングラブ、ストッキングフェチという嗜好を理解さえしてくれなかったのである。
そして大学入学後に付き合った二人の彼女達にとってはストッキングイコールただの靴下的な存在、バイトで指定されているからただ穿いている…という存在でしかなかったのだ。
唯一の理解者が真実であったのである…
美冴さんはこの僕の激情とも云える激流の熱いキスの想いが伝わったのか、まるで力が抜けたかの様に脱力し、カラダを僕に預けてきたのだ。
そして僕は美冴さんを強く抱き締めていく。
唇を外し、耳元からうなじへと這わせていくと、更に鼻腔にムスク系の甘い香りが広がり、心を昂ぶらせてくるのだ。
右手ではストッキング脚の爪先を弄り、左手で美冴さんの肩を抱く。
僕の左腕には、痩せた、華奢な美冴さんのカラダを感じていた。
あの頃より少し痩せたんじゃないかな…
そんな感覚が左腕に伝わってくる。
そして僕は一気に顔を下げ、スカートから露わになっている太腿に頬ずりするかの様に顔を押し付けていく。
太腿のピンと張ったストッキングのナイロン繊維が、ザラザラと僕の押し付けた頬を刺激してきていた。
ああ、これだ、これだよ、このストッキングの感触と、甘い香りだよ…
僕には堪らない香りと感触なのである。
そして僕は顔を太腿からゆっくりと下ろしていき、膝、すね、脚首、そして爪先へと伝わせていくのだ。
漂ってくるムスク系の甘い香りに、心がすっかり酔い痴れていた。
そして僕は顔を、いよいよ、五年間の憧れの、渇望し、羨望していたストッキングの爪先へと這わせていく。
美冴さんが失踪的に消えた後、朱美さんに約1年間お世話になり、女性の奥深さを教えて貰った。
だが、僕には、女性の神秘も大切ではあったのだが美冴さん亡き後にも心から切望し、渇望していたのはストッキングラブという、性的嗜好の満足と充足なのであったのだ。
だが、美冴さん以外からはそんな性的嗜好の羨望は、全くといっていい程に満たされはしなかったのである。
朱美さんは比較的脂性で汗かきであったらしく、脚の、ストッキングの爪先の匂いは激臭であったのだ。
そして朱美さんと同時に付き合いを始めた同級生の女子高生はストッキングイコールオバさんの穿くモノ…
というイメージを持っていて、全く持ってストッキングラブ、ストッキングフェチという嗜好を理解さえしてくれなかったのである。
そして大学入学後に付き合った二人の彼女達にとってはストッキングイコールただの靴下的な存在、バイトで指定されているからただ穿いている…という存在でしかなかったのだ。
唯一の理解者が真実であったのである…
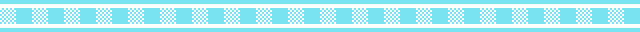
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える