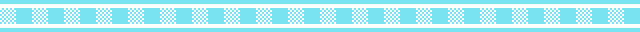
ぜんぶ俺の物〜ケダモノ弟の危険な独占欲〜
第2章 嘘つき
絆創膏をつけた長い指先を銃口のように向けると、ため息まじりに亜貴が言った。
「服もダサいし髪もぼっさぼさ。ずっと気になってたけど、それじゃあ旦那さんに愛想つかされちゃうよ」
「よ、余計なお世話」
仕事帰りのまま、いや、結婚式から手入れを怠っている黒い髪は、たしかに微妙なお団子になって頭の後ろで垂れている。服装は……、動きやすいTシャツに黒のパンツ姿で何が悪い。
「旦那さん帰ってくるまで時間あるんでしょ。整えてあげるから、きて」
「いい、いい」
慌てて両手を横に振った。
「ぷ」
「な、なに笑ってんのよ!」
「もしかして、俺のこと意識してる?」
その究極にいじわるそうな顔に絶句する。
(意識……するに決まってるわ!)
小さいころからあんなことやこんなことをされて、大学に上がるころには「好き」だなんて言われて。いくら弟だからって「ハイハイ、あの頃は大変でしたねー」なんて笑い飛ばせる問題じゃないだろ!
「警戒しなくたって何もしないよ。俺、いまは他に好きな人がいるし」
「え?」
そうだったの?
「なんだよ、母さんとの話聞いてなかったの?」
「あ。うん。ごめん」
そっか、片想いしてる人って私じゃなかったんだ。
「俺、準備してるから先に風呂でも入ってきたら?」
「準備?」
「そう、ヘアセットの準備。せっかくだからきれいにしてあげる」
リュックを掲げながら亜貴が言う。なるほど、あの中に美容師道具が入っていたわけか。
「中身、壊れなかった?」
「平気」
亜貴はさっそくリュックの中をごそごそと漁っている。危ない所を助けられておきながら、弟の良心を疑ってしまうなんて、姉として情けない。
「亜貴、さっきはありがとう」
「別に」
リュックの中身に視線を落としたまま、ぶっきらぼうな返答が戻ってくる。
「亜貴のおかげで助かった」
「そう」
「うん。本当にありがとう」
「ねえ寝室借りれない? リビングだとやりにくいかんじ」
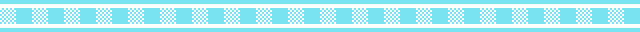
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える