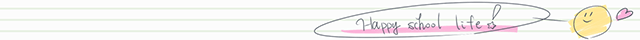
原稿用紙でラブレター
第5章 青いハートに御用心
『んでさ、俺とにのちゃんのことを有岡から聞いてたらしくて。だから同じ立場の俺に相談したんだって』
『ふ~ん。つーか有岡バラしてんじゃねぇよって話だよな』
『うんまぁ…でも別にそれ以上広がってないみたいだし』
『んで?お前なんて言ってやったの?』
『んー…まぁとりあえず想いは伝えた方がいいよって。俺も一か八かだったけどぶつかったよって』
『まぁなー。それで今があるんだもんなぁ…』
知念くんの話を翔ちゃんにしている最中、多分二人とも高校の頃を思い出していた。
どっちが先に告るかってバカみたいに競い合っていたあの頃を。
『そしたらさ、その子告白したことないから練習したいとか言いだしてさ』
『はっ、マジかよ!ウブな奴だなソイツ!』
『そうなの。なんかさぁ、一生懸命でいいなぁって思っちゃって。つい力入って色々パターンやってみたりしてさ』
『ふはっ!先生も大変だよな、んなことまで教えなきゃなんねぇって』
そう、色々やってみてる内に知念くんに情が湧いたというかなんというか。
まるで昔の俺を見ているようで。
だから今まで大ちゃんに色々と相談していたように、今度は俺が知念くんにとってそういう存在になれたらいいなって。
気持ちを共有したり理解してくれる人が周りに居ることがどんなに心強いか。
大ちゃんや翔ちゃんが居てくれたことが、俺にとってどれだけ心強かったことか。
そして告白の練習に付き合った後、最後に"頑張ったね"の意味を込めて頭を撫でてあげたら抱き着かれたんだ。
もちろんお互いそこにヘンな感情なんてなかったけど、何だか勝手に知念くんの保護者になった気分で。
知念くんも俺をお兄ちゃんみたいに思ってくれてのことだったんだと思う。
そこの、あのただの一度きりの場面を運悪くにのちゃんに見られてしまったんだ。
…この完全なる誤解をどう解いたらいいんだろう。
スーツのポケットから手探りでスマホを取り出して顔の前に掲げ。
常にLINEの一番上にあるそのアイコンをタップしようとして指が止まる。
浮かんだのは泣き顔を見せまいと強がる震えた背中と"一人にさせて"という言葉。
歯痒さより先に募った切なさはやり場を無くし、それ以上動かせなくなった手をパタリとシーツへ沈めた。
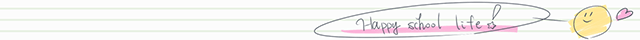
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える