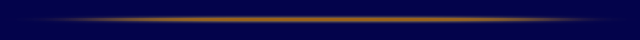
胡蝶の夢~私の最愛~⑪【夢路・ゆめじ】
第5章 《謎の女》
確かに、榊原家ほどの名門、五千石取りの直参旗本の奥向きに仕える奥女中があそこまで口が軽いのも考えものだ。奥向きは当主の私邸でもあるから、どのような機密、秘密が潜んでいるかは知れない。腰元たちは常に当主泰雅や正室泉水の近くに控え、内輪のことまで見聞きしている。それら一切が奥女中の口から外部に洩れては一大事であった。
もっとも、あの二人はまさか中庭に奥方が隠れているとは想像もしなかったに相違ないが。
「まあ、こうなることは時間の問題であったのやもしれぬ。心配することはない、時橋。私はこんな日がいずれは来るとは思うておった。人の心はうつろい易きもの。ましてや、我が殿は名うての女好きでいらせられる。大体、殿が私のような女子に眼を向けられたこと自体が端から奇跡のようなものだったのじゃ。大方は美しい花々に飽きて、いっとき少し変わった野の花をお摘みになられたのであろう。だが、ほんのお戯れでお摘みになるのであれば、いっそのこと、そっと野に置いておいて下されば良いものを」
まるで自分をあざ笑うかのような物言いには絶望が満ちていて、それは泉水の心の悲鳴のように時橋には思えてならない。
「お方さま、そのようなご自分を貶められるようなお言葉はお止め下さいませ」
「別に我が身を貶めているわけではない。真を申しておるまでのことよ」
泉水は抑揚のない声で淡々と言った。
「野に咲いていた花は所詮、野でしか生きてはゆけぬ。一度摘まれてしまえば、元には戻れぬ」
泉水は軽く首を振った。
「叶うものならば、戻りたいのう、時橋。あの頃に、槇野の家に居た頃に戻りたい」
まだ恋どころか、人を好きになることさえ知らなかった無垢な自分に。庭を駆け回り、木刀を振り回し、町に出ては様々な物や人を見、無邪気に大きな眼を煌めかせていた少女の頃に。
叶うなら戻りたい、帰りたかった。
「やはり、私はこの家では無用のものやもしれぬ。いや、泰雅さまにとっては、何の意味も魅力もない女子なのやもしれぬ。いっそのこと、帰ろうか、時橋」
力無く呟く泉水に、時橋は声高に言った。
もっとも、あの二人はまさか中庭に奥方が隠れているとは想像もしなかったに相違ないが。
「まあ、こうなることは時間の問題であったのやもしれぬ。心配することはない、時橋。私はこんな日がいずれは来るとは思うておった。人の心はうつろい易きもの。ましてや、我が殿は名うての女好きでいらせられる。大体、殿が私のような女子に眼を向けられたこと自体が端から奇跡のようなものだったのじゃ。大方は美しい花々に飽きて、いっとき少し変わった野の花をお摘みになられたのであろう。だが、ほんのお戯れでお摘みになるのであれば、いっそのこと、そっと野に置いておいて下されば良いものを」
まるで自分をあざ笑うかのような物言いには絶望が満ちていて、それは泉水の心の悲鳴のように時橋には思えてならない。
「お方さま、そのようなご自分を貶められるようなお言葉はお止め下さいませ」
「別に我が身を貶めているわけではない。真を申しておるまでのことよ」
泉水は抑揚のない声で淡々と言った。
「野に咲いていた花は所詮、野でしか生きてはゆけぬ。一度摘まれてしまえば、元には戻れぬ」
泉水は軽く首を振った。
「叶うものならば、戻りたいのう、時橋。あの頃に、槇野の家に居た頃に戻りたい」
まだ恋どころか、人を好きになることさえ知らなかった無垢な自分に。庭を駆け回り、木刀を振り回し、町に出ては様々な物や人を見、無邪気に大きな眼を煌めかせていた少女の頃に。
叶うなら戻りたい、帰りたかった。
「やはり、私はこの家では無用のものやもしれぬ。いや、泰雅さまにとっては、何の意味も魅力もない女子なのやもしれぬ。いっそのこと、帰ろうか、時橋」
力無く呟く泉水に、時橋は声高に言った。
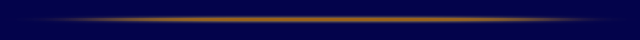
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える