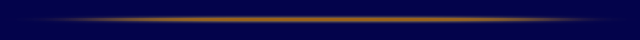
胡蝶の夢~私の最愛~⑪【夢路・ゆめじ】
第35章 哀しみの果て
喉の渇きを憶え、泉水は眼を見開いた。悪い夢を見ていたような気がする。いかほど眠ったのかも知れず、泉水は小首を傾げながら、ゆっくりと褥に身を起こした。
あれは、一体何だったのだろう。男に幾度も抱かれ、あられもない痴態を見せていた女は―。
そこで、ハッと我に返った。
思い出したくもない数々の場面が脳裡に蘇り、愕然とする。
あの女は、男の上に跨り淫らな声をを上げていたのは、他ならぬ我が身ではないか!
絶望が一挙に押し寄せ、思わず両手で顔を覆う。たとえ、本懐を遂げるためとはいえ、何ということなのか。元々は男を油断させ、その懐に入り込むための手段のはずだったというのに。今の自分は、完全にその手段に取り込まれた状態になってしまっている。
生理的に男を受け容れられないはずの身体がいつしか男を自ら迎え入れるまで淫らになっている。
泉水は無意識の中に、屋敷に帰ってきた夜を思い出していた。心では震えながら、歯を食いしばり、引き寄せられるままに泰雅の胸にもたれかかった―。首筋にかかる吐息や身体中をまさぐられる指の感触がおぞましくてならなかった。組み敷かれたときは、屈辱感に叫び出しそうになった。五年ぶりに泰雅をその身体に迎え入れたときは、溢れる涙を抑えるのに必死だった。
だが、泰雅と過ごす夜が重なる度に、何かが少しずつ泉水の中で変化していった。貫かれる瞬間の嫌悪感が次第に薄らいでゆき、触れられることに抵抗がなくなっていった。泉水自身は、その変化が泰雅を欺くために自分がわざと平静を装っているにすぎないのだと考えていたのだが、真実はどうだったのだろう。
夜毎、褥を共にする中に、いつしか泉水の身体は男の愛撫に馴れていったのだ。かつて幾度も泰雅と褥を共にしながら、いかにしても慣れることのなかった身が、どうして今更、こんなことになってしまったのか。それは泉水にも判らない。ただ、二十三歳という女としては盛りの歳を迎え、泉水の女体も成熟し、微妙に変化してゆきつつあるのかもしれない。
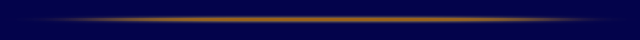
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える