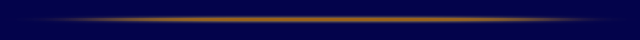
胡蝶の夢~私の最愛~⑪【夢路・ゆめじ】
第34章 涙
どれくらいの間、そのままでいただろう。ふと気付いた時、既に雷は止んで、周囲は嘘のような静けさの中、ただひそやかな雨音だけが響いていた。
―す、済まねえ。
狼狽えて謝る兵庫之助に、泉水は微笑んで首を振った。
―お前さまのお陰で、私、少しも雷が怖くはありませんでした。
不思議なことに、たとえ布団越しではあっても男に抱きしめられていたというのに、泉水は少しも恐怖も不安も感じなかったのだ。それどころか、兵庫之助の腕に抱かれていると、まるで幼い頃、やはり雷に怯えて父や乳母の懐で震えていたときのように、限りない安らぎを憶えた。
その時、泉水と兵庫之助の視線が交わった。
いつも一緒にいて、互いに見飽きるほどにもう顔は見ているはずなのに、あたかも初めて見つめ合うようなほど食い入るように互いの顔を見つめた。兵庫之助の大きな手で引き寄せられても、泉水は抗いもせず、素直にその腕に抱かれた。
やがて、静かにほのかに熱を帯びた唇が降りてきて、泉水の唇をしっとりと塞いだ。三月(みつき)以上も共に暮らしていながら、兵庫之助が泉水に触れたのは、これが二度めであった。最初は二ヶ月月ほど前、恋情に耐えかねた兵庫之助が泉水を組み敷こうとしたのだ。が、その時、泉水は泣いて嫌がった。そして、兵庫之助に初めて我が身の秘密―男を身体的に受け入れられないことを告げた。
以来、兵庫之助は一度たりとも泉水に手を伸ばしてきたことはない。
最初はついばむような軽い口づけを幾度か繰り返した後、やがて兵庫之助は深く口づけてきた。それは次第に貪るような烈しいものに変わっていった。男の舌が口の中に侵入してきたときも、何故か泉水は抵抗感もなく口を開いて、受け容れていた。烈しい口づけの後は、二人、一つの布団に寄り添い合って朝まで眠ったのだ。
兵庫之助は口づけ以上のことをする様子はなかった。もし仮に兵庫之助が最後まで求めてきたとしたら―。果たして、自分はどうしていただろうかと、泉水は朝になって考えた。もしかしたら、泉水はそれでも、兵庫之助を受け容れて―現実的にそれが可能かはどうかは判らないけれど、受け容れようとはしたのではないかと思う。
―す、済まねえ。
狼狽えて謝る兵庫之助に、泉水は微笑んで首を振った。
―お前さまのお陰で、私、少しも雷が怖くはありませんでした。
不思議なことに、たとえ布団越しではあっても男に抱きしめられていたというのに、泉水は少しも恐怖も不安も感じなかったのだ。それどころか、兵庫之助の腕に抱かれていると、まるで幼い頃、やはり雷に怯えて父や乳母の懐で震えていたときのように、限りない安らぎを憶えた。
その時、泉水と兵庫之助の視線が交わった。
いつも一緒にいて、互いに見飽きるほどにもう顔は見ているはずなのに、あたかも初めて見つめ合うようなほど食い入るように互いの顔を見つめた。兵庫之助の大きな手で引き寄せられても、泉水は抗いもせず、素直にその腕に抱かれた。
やがて、静かにほのかに熱を帯びた唇が降りてきて、泉水の唇をしっとりと塞いだ。三月(みつき)以上も共に暮らしていながら、兵庫之助が泉水に触れたのは、これが二度めであった。最初は二ヶ月月ほど前、恋情に耐えかねた兵庫之助が泉水を組み敷こうとしたのだ。が、その時、泉水は泣いて嫌がった。そして、兵庫之助に初めて我が身の秘密―男を身体的に受け入れられないことを告げた。
以来、兵庫之助は一度たりとも泉水に手を伸ばしてきたことはない。
最初はついばむような軽い口づけを幾度か繰り返した後、やがて兵庫之助は深く口づけてきた。それは次第に貪るような烈しいものに変わっていった。男の舌が口の中に侵入してきたときも、何故か泉水は抵抗感もなく口を開いて、受け容れていた。烈しい口づけの後は、二人、一つの布団に寄り添い合って朝まで眠ったのだ。
兵庫之助は口づけ以上のことをする様子はなかった。もし仮に兵庫之助が最後まで求めてきたとしたら―。果たして、自分はどうしていただろうかと、泉水は朝になって考えた。もしかしたら、泉水はそれでも、兵庫之助を受け容れて―現実的にそれが可能かはどうかは判らないけれど、受け容れようとはしたのではないかと思う。
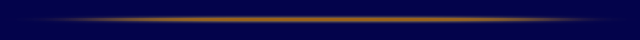
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える