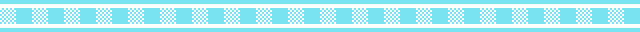
例えばこんな日常
第33章 FLAVOR GALLERY vol.3
19時を回りようやく夕焼けの準備を始めた空。
同じく俺たちも店の片付けに取り掛かる。
刺すような太陽も、磯の香りを纏う潮風も、キラキラと輝く波も。
何ひとつ好きにはなれなかった三年間。
けれどこうして毎年続けることができたのは、唯一好きな存在が隣にあったから。
「にのー、テーブル全部オッケー?」
「んー、こっちオッケー」
せっせと椅子を運ぶ後姿は晒された二の腕がこんがり焼けて際立っていて。
相葉くんに誘われて始めた海の家でのバイトも今年で最後。
最後の夏が終わる。
大嫌いな俺の夏が終わってしまう。
「うわっ、めっちゃ音漏れしてんじゃん!」
って急に弾むような声色で相葉くんが駆け寄ってきた。
海水浴場に併設の野外音楽堂ではフェス真っ最中。
人の気配がほぼないこの海岸と違い歓声がこだまする。
きっとセンチメンタルなこの気分は遠くから漏れてくるあの音のせい。
砂浜と夕焼けとラブソングだなんて。
どんな王道シチュエーションだよ。
店先から一望できる海を前に隣にはいつもの横顔。
"にの真っ白なんだから少しは日焼けしなきゃ"と無邪気に笑う白い歯がそこに重なる。
そんな誘い文句無くたっていいのに。
俺は相葉くんの誘いならどんなことも受けるから。
一緒に居れるならどんなことだって。
ザザ…と寄せては返す波に乗ってふと間近に聞こえてきた歌声。
目を上げれば真っ直ぐ海を見つめて特徴的なメロディを口ずさむ横顔が。
それは今しがた流れていたラブソングで。
しっかりとサビを歌い切ったその横顔がふいにこちらを向いた。
「にの、あのさ…」
風になびく茶色がかった髪が揺れて。
「また来年も来ない?ここ」
「…え?」
日焼けした肌に浮かぶ煌めく汗に見とれそうになりながら。
「遊びに来ない?またここにさ」
「え?それって…」
波の音にも潮風にも負けないくらいはっきりと。
「…俺と居てくれない?来年も、その先も」
そう告げられて、射抜かれたように息が止まった。
そんなクサい台詞どこで覚えたんだって言いたくなるけど。
でも。
「…うん、ずっと居る」
どんな流行りのラブソングも敵わない。
世界にひとつだけの、最高の歌詞だって思った。
end
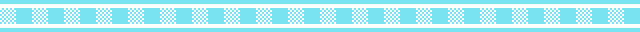
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える