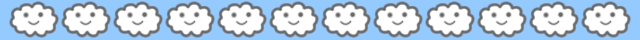
百鬼夜行左藤家黙示録
第14章 友情の価値は
しかし何日たっても義明は現れなかった
これはただ事では無いと言うことだ
昔まだ幼小期に大きな公園にある
トランポリンで遊んだとき
跳ねて飛んでおもいっきり沈んだら
さらに大きな跳ねをした記憶がある
それは沈めば沈んだだけ高く舞い
その沈んでいる時にこそ楽しみがあった
まさにこんな時の義明はその沈みであり
溜めた分だけ大きな力を吐き出す
「ピンポーン」
そしてそれは今まさに始まるだろう
そう確信するほど嫌な予感の拭えない
このインターホンの音は
憂鬱や悲哀を孕んだ弔鐘のように聞こえた
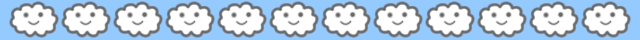
 作品トップ
作品トップ 目次
目次 作者トップ
作者トップ レビューを見る
レビューを見る ファンになる
ファンになる 本棚へ入れる
本棚へ入れる 拍手する
拍手する 友達に教える
友達に教える